スペシャル無料講座「考える力をつける勉強法」― 幸せな大人になるためのゴールデンルート ― ④

2.ロボット人間とマニュアル人間。考えることを放棄してしまう、思考パターンとは。
(1)受験生を取り巻く、ある特殊事情。
さて、それでは次に、「なぜ人は、自分の頭で考えるということを徐々に徐々にしなくなっていってしまうのか。」ということにつき、お話をしていきたいと思います。
再び受験生を例にとってみましょう。受験というのはある意味特殊な世界、異常な世界と言ってもいいでしょう、とにかく普通ではない世界だと言うことができます。というのも、本来なら長い間じっくり時間をかけてコツコツと培ってゆくはずの実力を、基本的には「入試本番というタイムリミットがある状況において、できるだけ短期間で、できるだけ簡単に、できるだけ大きく伸ばしてゆく」ということを目的にしているからです。
まあ、それはそれで面白い世界なので、チャレンジしてみることはいい経験、やり方によっては自分自身の成長・発展につながってゆくことも確かです。「受験という限られた枠」の範囲でいかに考える勉強をやってゆくか、こういうことに挑戦してゆくことはとてもワクワクする体験ではあります。だからこそ、私は受験生の指導をすることをライフワークとしてずっとやって来ているのですが、やはり受験生を見ていると気の毒に思えてくるケースが多いです。毎日毎日、来る日も来る日も、ひたすら塾や予備校において教わってきた解法パターンや重要知識の記憶に勤しむ日々。きちんと理解した上での記憶であればまだよいのですが、そんな余裕がある子は決して多くはない。大抵の子は、与えられた知識をただそのまま無理やり飲み込んで、吸収しようとしているような状態。本当に勉強が辛そうです。そしてもちろん、徐々に入試改革がなされてきているとはいえ、基本的には現状ではまだまだ、その記憶がどれだけ完璧にできているのか、それを試す場がテストであり入試であり続けているわけです。
ところがこれは、そもそも無理がある話なんですよね。テストや入試という、いわゆる本来は「実力」を試す場であるはずのところで、実力とは無関係な、記憶力を試している。もちろん、記憶は大事ですよ。特に小さい頃は。理論理屈を抜きに、とにかく覚える。覚えて覚えて覚えまくるうちに、自分の中で、自分の頭の中でポッと開けてくる回路が出てくる。あるいは、古文や漢文など、多くの古典文学に触れてゆくこと自体が、その子の感情面・情操面を培い養ってくれる。そういうことはもちろん、大事なことです。
しかし、いつまでも何でもかんでも記憶・記憶・記憶でいいのか、ということです。どんなに自分の頭を使って勉強したとしても、残念ながらそれは例えば選択式テストの答案用紙の上からは、基本的には見えてこない。なぜなら、覚えているかどうかを試すテストだからです。そうすると、どんなに苦労して自分の頭で考えても、結局は「覚えているかどうか。」が試されるわけですから、子どもたちも「じゃあ、もう手っ取り早く、解き方を覚えちゃえ。だって楽だし。」ってなってしまうわけです。
で、お父さんお母さんも、どうせテスト結果を見せてもらうのなら、30点のテストを見せてもらうよりは、できれば80点のテストを見せてもらいたい、というのが親心というものなんですよね。そうすると子どもの方も、「お父さんお母さんの喜ぶ顔が見たい。」と思うので、ますます解法パターンをせっせせっせと記憶しては、80点のテストをお父さんお母さんに運ぶ、ということがもう、仕事みたいになってくるわけです。こうなってくるともはや、「解法暗記・80点テスト配達マシーン」ですよね。
ところが、あるとき気づくわけです。「あれ!?何かがおかしいぞ。記憶だけが試されているはずだったのに、記憶だけでは点数が伸びていかない。」という事実に。例えば入試直前に数学の問題を解いているときに。例えば、国語の読解問題のテスト直しをしているときに。「ダメだ。全然分からない。どうしよう。もう入試まで時間がないのに、いったいどうしたらいいんだろう。」


(2)「キミ、だれ?」(笑)
どうしてこんなことになってしまうのでしょうか?どうして、こんな状態になるまで気づかないのでしょう?
それはやはり、「人間は、もういよいよ限界、っていうことになるまで、気づかないし、気づこうとしない。」っていうことがあるからです。私の場合、お菓子ですね。結構お菓子が好きで、家庭教師先で「先生、ここのケーキ、とっても美味しいんですよ。」なんて言われて出されたりすると、ペロッと平らげて、で同じ日にまた別の生徒さんのお宅に行ったとき、「先生、ここのお饅頭、人気なんです。行列ができるぐらい。」なんて言われて出されたすると、またペロッと平らげて…家に帰ってくれば帰ってきたで、「今日はよく働いた。ご褒美に菓子パンでも食べようか。」とやっていたら…ある日自分が写った写真を見たときに、「キミ、だれ?」ってことになりました(笑)。それ以来、お菓子は一切お断りすることにしています。だって、太るのは簡単ですが、ダイエットするのってホント大変でしたから。
いやあ、もう、人間、そんなもんなんですよね。やっぱり。気づかないんですよ。自分のことは。他人のことなら気づくんですけどね。「人は自分を映す鏡」とは言いますが、なかなかなかなか。
ですから、勉強の場合も、特に受験ですよね。受験の場合も、なかなか気づかない。気づこうとしない。「まだ、もうちょっとイケるやろ。」って感じで。イケないイケない(笑)。間違いなくキミが行ってる先、行き止まりやから。そう言ってくれる人がそばにいる場合はまだいいんですが、みんなして行き止まりに向かって突撃しているような状態の場合、結構笑えない話になってくるのではないでしょうか。
(3)成績いい子こそ、実は危険。「○だけちょうだい人間」のたどる悲しい末路とは。
家庭教師をしていると、結構いらっしゃるんです。「成績はいいのに、実力が?な子」っていうのが。「あれ!?この子、こんなに偏差値高いのに、何これ?」みたいな(笑)。で、よくよく見てゆくと、原因が分かります。「ああ、そういうことだったのね。それなら、わかるわかる。」と。つまり、「○をもらうこと」「偏差値を上げること」にばっかりに意識が行っていて、「分からないこと・理解していないことについて、しっかり分かるまで理解できるまで考える。」ということに意識が行っていないんですね。そうするとこれは、残念ながら「基本的には一から勉強やり直し。」、ということになるんです。もちろん、初回授業からそんな風には言わないですが、徐々にそういうことに気づくように促してゆくわけです。いずれにしても、「えー!?」ってなりますよね。「そんなはずはない。私は結構成績取れてるし…ね、お母さん、この先生何か一から勉強やり直すみたいな変なこと言い出してる。何とか言ってよ。」みたいな感じになったり。
でも、お母さんはもちろん、薄々気づいているんです。「この子、確かにテストで点数は取れてるけど、悪いときはとことん悪い。分野によっては全く理解できていないのかもしれない。実力がないんだわ。」と。
ところが、そもそもこの子が「○だけちょうだい人間」になってしまった理由が、実は「お父さんお母さんにほめられたい。」だったりすると、結構厄介なんです。この子にしてみれば、「お父さんお母さんの望むように、点数を上げてきた。」のに、ある日突然「おまえのやってきたことは間違っていた。」みたいに言われるわけですから。騙されたような、裏切られたような、複雑な気分になります。
「じゃあ、私は一体どうしたらいいの?」ここで気持ちを切り替えられればよいのですが、妙に育ってしまった「プライド」が邪魔してしまうと、なかなかスムーズには進みません。逆に言うと、そこを乗り越えさえすれば、もともと勉強習慣はできていて知識自体は持っている子です。「自分の頭でしっかり考えて勉強する」というやり方によって、それまで頭の中でバラバラに存在していた知識を、実際に使える形でつないでゆくことができれば、比較的短期間で実力をUPさせることも可能となってきます。

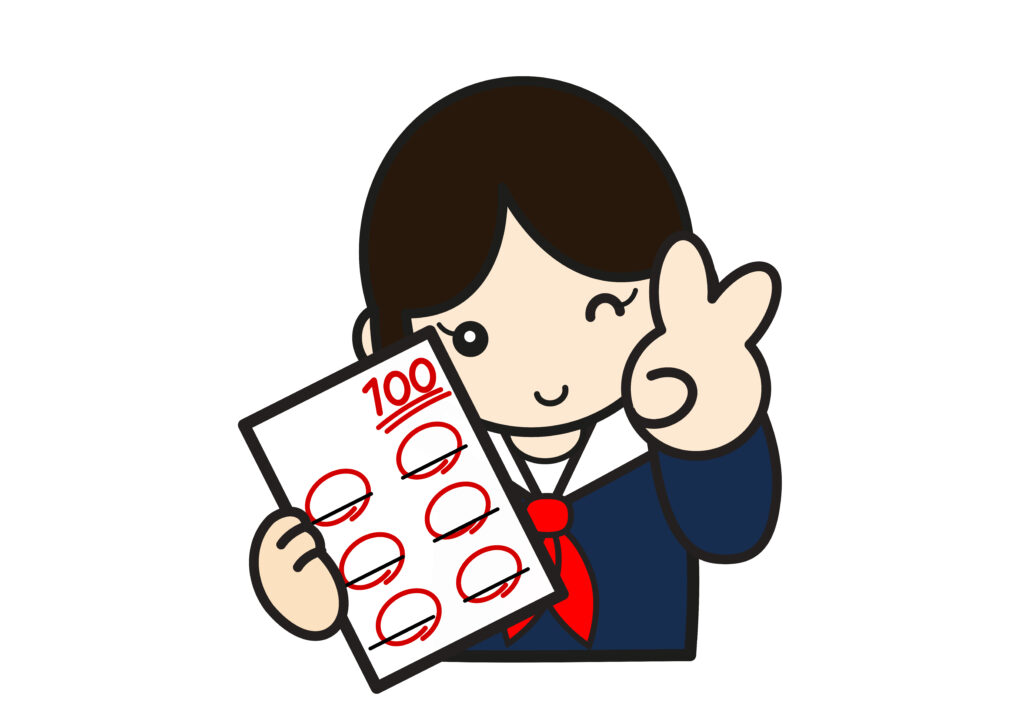
(4)気づかないと手遅れになる。「中間期末病」は、大人になってからも続く。
「とりあえず急場をしのいで、何とかしようとする姿勢」のことを、私は「中間期末病」と呼んでいます。すなわち、中間テストや期末テストの直前に、それこそ一夜漬けに近い状態でとにかく知識を頭の中に叩き込んでゆくような勉強の仕方です。
このような形で勉強している中学生は結構いるものです。そういった子たちの特徴は、「いい成績を取りたい。」という気持ちが存在し続けているということです。もちろん、その気持ち自体は決して悪いものではないのですが、問題は「成績さえ良ければそれでいい。」という気持ちにつながることが往々にしてある、と言うことです。
つまり、中間・期末テストの成績は良いため、一見学力が高いように思えるのですが、実際実力問題を解いてもらったり、実力テストの結果を見させてもらうと、「あれっ⁉」となることがしばしばある、ということです。
こういう子たちは、英語・数学・国語など、本来思考力を養成することが目的であるはずの科目ですら、何とか「暗記」で乗り切ろうとします。ある程度パターンが記憶できているわけですから、中間・期末テストレベルであれば8割から場合によっては満点を取ることもよくあります。
ところが範囲の広いテスト、実力テストや模擬試験になると、途端にその実力が思わぬ形で露呈してしまうこととなります。1度や2度そういう形が出たぐらいでは、「たまたま調子が悪かったから…。」と、自分自身の真の実力を正面から受け止めようとせず、自分のやり方を変えようとはしません。
そういった何となくの勉強を繰り返してゆくうちに、そのような勉強の仕方で凝り固まってしまい、もはや「似たような問題しか解けない人」となってしまい、高校受験をする際にもひたすら「やった問題が出ますように。やった問題が出ますように。」と、受験勉強がいつの間にか祈祷競争のような様相を呈するという、奇妙な事態になってまいります。
このような子たちの個人指導を依頼された場合には、「何が目的なのか、どこを目指すのか。」ということを徹底的に話し合うことから始めます。そういう子は、最初は旧態依然として自分のやり方にしがみつくこうとしますが、執着している価値観をいったんリセットして新たな価値観をゼロから作り上げることの方がよっぽど楽しく成果につながるということに気付くと、スッキリした表情で勉強に向かうことができるようになります。
そういった話をする際には、「そのやり方はうまくいかない。」という視点から見ることももちろん大事ですが、「そのやり方は、キミらしいやり方か?」「そのやり方は、キミが心の奥底から望んでいるやり方か?」という観点から話をすることも同じぐらい大切です。前者は大人の見方、後者は子どもの見方です。大人的な視点と子ども的な視点。両者のバランスがうまく取れてこそ、本当の意味のやる気・モティベーションが湧いてくるものだからです。
(5)ロボット人間とマニュアル人間。
機械的に作業をこなすことだけしかできない人。指示された通りにしか動けない人。このように表現すると、まるで仕事ができない人かのように思えるかもしれませんが、決してそうではありません。
型式化された繰り返しのタスクについては、何も考えずに手が動き足が動き体が動くようにすることがまず大切です。そのためには、パターン化され得る部分をしっかりとまとめ上げたマニュアル作成は必須であり、先人の作り上げたマニュアルはその分野に携わる者にとってはバイブルとも言うべき重要なものです。
また、自分の以外の人がリーダーシップを取る役割を担っている場合、その人の指示や命令に従わないことは、それこそ船頭多くして船山に上るとなってしまい、下手をすると自分を含めチームみんなに迷惑がかかる事態を招きかねません。ですから、何でもかんでも自己主張を全開にして自分オリジナルのアイディアを叫び続けるのは、慎むべき場面が多々あるだろうということです。
しかし…しかし、です。創造性を発揮すべき場面、個性をアピールすることがみんなの利益になるような場面においてまで、借りてきた猫のようにひたすら黙り続け、周囲の意見にただただ同調するのみというのでは、信頼も信任も得ることは厳しいでしょう。
受験勉強においても、全く同じことが言えます。受験勉強において型式化されたタスクとは、場面が変わり問題が変わったとしても普遍的に成り立つ経験則から導き出される公式・ルールに則った勉強内容のことを指します。そうした勉強内容につき、ゼロから自分でオリジナルの方法を編み出そうとする努力は、時には必要だと言えるかもしれませんが、多くの場合はする必要のない回り道をすることとなり、賢明な選択ではないことでしょう。
ですからそういう勉強内容については、金太郎飴的な定式的練習を厭わずに愚直に問題を解き続けて、当該学習項目を自分のものとしてくという態度が求められます。ここのところに関しては、「ロボット人間」で構わない、いや、むしろロボット人間、解答マシーンと化すことこそが正解だと言うことができるでしょう。その際は取扱説明書・操作マニュアルに相当する公式・解答解説集が本領を発揮することでしょう。
ここにおいては、「ロボット人間」「マニュアル人間」たり得ることこそ、血の通った人間としての自分が心から願ってやまない志望校合格のために必要不可欠です。
基本を十分に理解した分野・学習項目については、科目を問わずこうしたことが当てはまります。
一方、そういった単純・機械的手法がそぐわない場面も、もちろん存在します。それは、新しい単元を学ぶときです。
「えっ⁉新しい単元を学ぶときこそ、内容が全く分からないのだから、繰り返し学習が大事なんじゃないの?」そう思うかもしれませんね。もちろん、新しく学習した単元は一度理解し身に付いたと思っても、時間が経つと内容がすっかり頭から離れてしまう、ということが少なくありません。ですから、何度も何度も学習内容のおさらいをすることが極めて大切です。
しかしそれは、あくまでも「基本を学び終わった後」の話です。基本を学び終わった後は、自分の中で当たりまえになるまで反復練習をすることが大切ですが、基本を学ぶまさにその時には、頭をフル回転させ、目の前の学習内容に対して徹底的に考え抜くことが何より大事です。なぜなら、そのプロセスを通して当該学習項目の知識とその項目に対応する思考力が身に付くからです。
かけ算・割り算をおろそかにしてしまうと、分数がなかなか身に付かなくなり、分数をおろそかにしてしまうと、比の単元が身に付かなくなり、比の単元をおろそかにしてしまうと、比を応用した文章題全般が身に付かないということになってしまいます。
文法をおろそかにしてしまうと、文の意味がつかめなくなり、文の意味をおろそかにしてしまうと、段落の意味がつかめなくなり、段落の意味をおろそかにしてしまうと、文章全体の意味がつかめなくなり、文章全体の意味をおそろかにしてしまうと、要約問題など文章全体に関わる設問が全く分からない、ということになってしまいます。
算数をおろそかにしてしまうと理科が分からなくなり、理科をおろそかにしてしまうと国語が分からなくなり、国語をおそろかしてしまうと、社会が分からなくなり、社会を含め勉強の基本をおろそかにしてしまうと勉強自体が嫌になってしまいます。
このように、1つをおろそかにしてしまうと他の様々な分野や科目にその影響が波及してゆき、気付いたら膨大な量の「不得意」を抱えることになりかねません。
ですからどうか、新しく単元を学ぶときには、新鮮な気持ちで頭もニュートラルにして、楽しく遊ぶ中で初めて勉強というものに気付いたら触れていた幼子のような純粋な態度で学習項目に向かうようにしてください。そうすれば、当該学習項目の方からあなた自身に優しく話しかけてくれるはずです。


(6)AI時代。「考える大人」として、社会を歩く。
昨年からの生成AIブームに始まり、もはやビジネスの世界では「AIを使うかどうか」ではなく「AIをどのように使うのか」ということに議論がシフトしています。かつては計算タスクをこなすものとして算盤が計算機に取って代わられたように、私たちがこの両手とマウス・キーボードでこなしていた作業と演算の大半は、もはやAIがこなすのが当たり前の時代になっています。
そんな中、私たち人類はいかにして考え、いかにして仕事をしてゆけばよいのでしょうか?
その答えは、「他者とは一線を画するかけがえのない私」とは一体何者か、という哲学的問いから派生して出てくるものでありましょう。つまり、前代未聞のこのAIブーム、いや、AI時代の到来によって我々人間は各々の自我とそれに根ざした個性というものと否が応でも向き合わざるを得ないのです。
全く同じ型のスポーツカーに乗っている人同士が決して同じ人間ではないのと同じように、全く同じAIを使っている人同士も決して同じ人間ではないのです。
エレキギターを演奏する人は自分の手足のようにギターを操りますが、決してその手がギターと文字通り一体になるわけではないのと同じように、AIを自分の分身のように使いこなす人がAIと一体化してしまうことはあり得ないのです。
散髪屋で、便利なバリカンに嫉妬し焦りを覚える理容師さんが存在しないのと同じように、パソコンの画面の前で、便利なAIに嫉妬し焦りを覚えるビジネスマンは存在しない…はずです。本来は。
しかしなぜかAIの場合だけ、「自分の仕事はAIに奪われてしまうのではないか?プログラミングができないと自分の存在価値はなくなってしまうのではないか?」そんな不安を胸に抱いてしまう人が少なくありません。
ですが、考えてみれば妙だと思いませんか。不安になったらすぐに転職するというのなら、今後の人生で一体何回転職が必要になるのでしょうか?人類皆がこぞってプログラミングに勤しんだのなら、一体誰がそのプログラミングに必要な電力を供給してくれるのでしょう?
全てのものには個性があり、その個性に適した役割が存在しています。孔雀のように色とりどりの翼を望むからと言って、タンチョウヅルは自らの翼を虹色に染め上げるでしょうか?「こんな鳴き声では可愛がってもらえない。」と言って、セントバーナードがトイプードルの鳴きまねを練習するでしょうか?
子どもたちは、見ています。私たち大人がどう感じ、どう生きているのかを。他者と自分を比べることが力になるのなら、その比較の視点は大いに持つべきです。「あの人のこういうところが素敵だな。自分も見習おう。」「あの人は、こうすることができる人だな。素晴らしいことだ。自分も実行してゆこう。」これは、他者という鏡をうまく活用できている例ですね。こういう場合実際には、他者という鏡を通して人は自分自身を見つめているのです。
しかし、他者という鏡をいつの間にか自分の不安と恐怖を映し出すスクリーンのように見てしまうと、そこから悲劇が始まります。嫉妬。妬み。嫉み。貪欲。強欲。こういった負の感情を持つとき、人は自分らしさを失います。自分という人間を見失います。
そうなってしまったときは、まずは深呼吸をして、過去でも未来でもあなく現在の自分をそっと見つめてみます。そうすると、今の自分という存在はあり得ないぐらいの数の偶然という名の必然と奇跡と縁によって出来上がっていることに気付くでしょう。
そういった時間を一瞬でも持てたとき、その人は本当の意味の思考を得ることができます。不安から出た雑音でも恐怖によって生じた騒音でもなく、そっと自分に語りかけてくる優しい声。それこそがあなた自身の本来の思考の声であり、あなた自身なのです。
そういったピュアな状態により近いのは、もちろん私たち大人ではなく生まれてからまだ長い歳月を過ごしてはいない子どもの方です。しかし、私たち大人にも、私たち大人の内面にも、ちゃんと赤ちゃんのときから大切に慈しまれ育てられてきた「内なる子ども」が存在しています。好きな漫画を読んだとき、大声で笑ってみたとき、突然のことにビックリしてしまったときなど…人が本来の自分、優しくて純粋無垢な自分に触れる機会は毎日訪れています。
「子どもを見守るのが大人の役目」。もちろんそうですが、子どももまた私たち大人の一挙手一投足に目を向けています。言葉で語れることと、そうでないこと。伝えるべきことと、伝わること。
この地球において古来から受け継がれてきた大切な何かとともに、今日もあなたからあなたのお子さんに大切な何かは受け継がれているのです。
(7)不登校の子。学校に通うことがゴールとは限らない本当の理由とは。
何かの出来事がきっかけとなって、学校に行かなくなる。あるいは、明確な何かがあるわけではなかったが、ある日突然、学校に行かなくなる。行けなくなる。我が国においては、不登校の子どもたちの存在が社会問題となってから久しい今日です。
しかし、よくよく考えてみると、不登校は果たして「問題」なのでしょうか?もちろん、いじめや体罰によって不登校になった子どもたちの親御さんや家族の方々は、想像を絶する精神的・肉体的苦痛とともに日々の生活を送っていらっしゃることでしょう。「一体いつまでこんな状態が続くんだ?もう、耐えられない。このままでは家族全員が倒れてしまうか解散するしかなくなってしまう。」そのように追い込まれた状況になることも少なくありません。
ただ、そういった辛い状況の最中にあっても、ふと気付くことがあります。「なんか、うちの子、成長したんじゃない?」「なんか、ついこないだまで気にしてたことが気にならなくなってるみたいだし、なんか、こないだまで無理だったことができるようになってる。」あるいは、「ものすごく理不尽なことばかりで、我慢の限界だって思ってたけど、家族みんなで久しぶりに会話をたくさんしたし、お互いの思いも確認できた。これって、かけがえのないことだよね。」と思ったり。
こんなとき、「この子の不登校は『問題』なのかな?解決すべき課題なのかな?なんか違う気がする。」と思えてきたりします。そうすると、「確かに、学校の友達ができないままでいるのは寂しいことかもしれないけれど、今は家族の絆を大切にして、この子らしさ、この子のペースを見ていきながら、この子が心身ともに元気いっぱいになれるサポートを家族全員でやってゆくことがベストなのかもしれない。」という気持ちが湧き上がったりもします。
そうすると、「何が何でもとにかく再び登校できるようにしてゆかないと。」と、追いつめられていた精神的苦悩・肉体的苦痛に耐えられなくなっていた状態から、少し力の抜けた、もう少し長期的な視野で長い目でお子さんを見守り支援してゆく環境が、家族の中で作られることとなります。
学校に行くもよし。学校に行かぬもよし。勉学に励むもよし。自分のペースで無理なく勉強するのもよし。
自分はどうしたいのか。分からない。じゃあ、今は考えるのをやめておこう。
自分で考えるのは嫌だけど、誰かの考えを聴くことはやってみたい。じゃあ、今は聴くことをしてみよう。
とにかく今は学校のことを考えたくない。考えられない。じゃあ、何も考えずに外に出かけてリフレッシュしよう。
何が正解かは分かりません。そもそも、正解を出そうとすることすら必要ないのかもしれませんし、やるべきではないのかもしれません。
考えすぎもよくないけど、何も考えないのも余計に疲れる。
これは考えられるけど、こういうのは今はいいかな。
その時々に応じて。気分に即して。
そんな中でも、いつでも忘れないでいたいことがあります。それは、人生は長く、人生は一瞬であるということです。
長い人生。これからどうにでもなるさ。だから焦ることはない。
今という瞬間はもう二度と訪れることはない。だからひと時ひと時を大事にしてゆこう。
家族みんなのバランス感覚を大切に。それぞれの個性を大切に。
答えは、私たち一人一人の中に存在しています。


(8)「考えない方がラク。」って本当か?誰にも訪れ得る、ターニングポイント。
ある男の子(Yくんとします。)の話です。Yくんは、小学2年の後半から小学3年にかけて、色々なことにつきうまくいかないことや悩み・なかなか決められないことが出てくるようになりました。もともと好奇心旺盛であったため、勉強も運動も、趣味も遊びも、あれもやりたい、これもやりたい、となっていた一方、何か軸になるようなもの、「これだけは形にしておきたいな。」と思えるものが出てくるといいな、と考えることもありました。
そんな風にいろいろと悩んだり迷ったりして2年以上の年月が経ち、「お前、結局どうするんだ?あっという間に小学校卒業になるぞ。」とお父さんに言われたりもしていました。しかし、何か目標に向かって集中して取り組もうとすると、なぜか「これが僕のしたいことじゃない。」そんな思いが頭をもたげることが続き、もう一体自分は何がしたくて何が嫌なのか、ホントはやりたいけど面倒くさいし楽したい気持ちが勝ってしまってやる気が湧かないだけなのか、何が何だか訳が分からなくなってしまいました。
そのような煮え切らない状態のYくんをお父さん・お母さんは半ばあきらめたような状態で見守っていましたが、ある日、いつものように色々と話をしている中で、「今はこれ。これが達成できたらこれ。これが実現したら、これにチャレンジする。」という形で明確な答えをYくんが出したのです。「えっ⁉ホントにそれでいいのか?」半信半疑でお父さん・お母さんは彼に尋ねましたが、決意が揺らぐことはありません。
あまりにもあっけなく決めてしまったので、なんだか拍子抜けしたみたいになってしまいましたが、その日以来、Yくんはまるで人が変わったように真っすぐ目標に向かって集中するようになったのです。
さて、ここで疑問が出てきますよね。「決意した日、Yくんは文字通り生まれ変わったようになったのか?」ということです。その答えはイエスとも言えるし、ノーとも言える気がしています。
大きな決断を下し、そこから見違えるように1つの目標に向かって努力を継続できるようになったという意味では、その決断を下した瞬間に生まれ変わったと言えるほどの大きな変化があったと言えるでしょう。
一方、その大きな変化は実は日頃からYくんなりにずっと考え続けていたからこそ、とろ火でコトコト煮込んでいた料理がじっくりゆっくり時間をかけて出来上がるように、毎日ちょっとずつの変化がゆっくり時間をかけて大きな変化へとつながっていったとも言えるかもしれません。
どちらが正しい答えなのかは、ひょっとするとYくんにもずっと分からないままかもしれませんね。
とにかく1つ言えることは、「何の準備もしていないのなら、物事は偶然任せになってしまう。」ということです。時には流れに身を任せることが望ましいときもあるかもしれませんが、人生という航海は選択と舵切りの連続である以上、やはり毎日コツコツと意識的に考え選び続ければ、必ずや、意識的に選択した自分の人生というものが少しずつ出来上がってゆくことでしょう。
受験本番で迷ったとき鉛筆を転がすのも悪いとは言いませんが、できればそういった大事な場面においては、いかにして選択すべきか、という判断基準を意識的に持てるよう、日々の勉強の中で練習しておくことをおすすめいたします。

